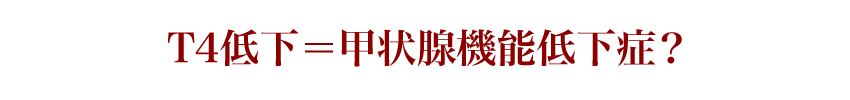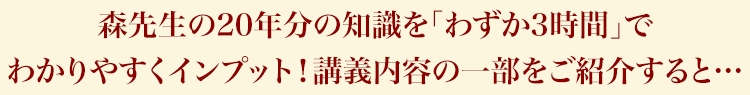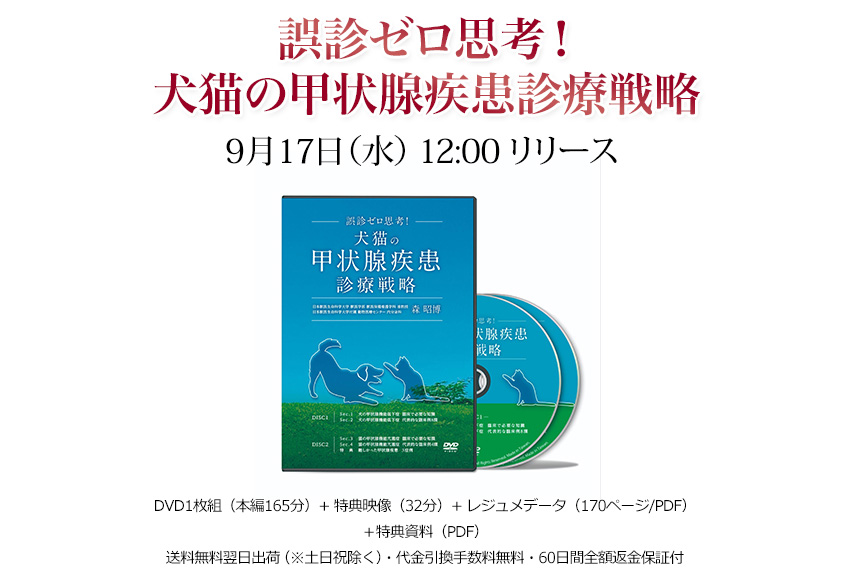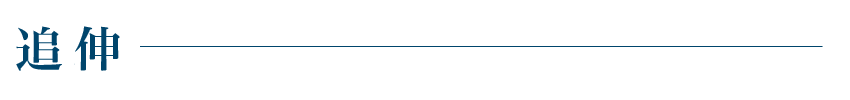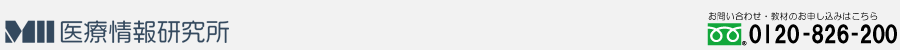
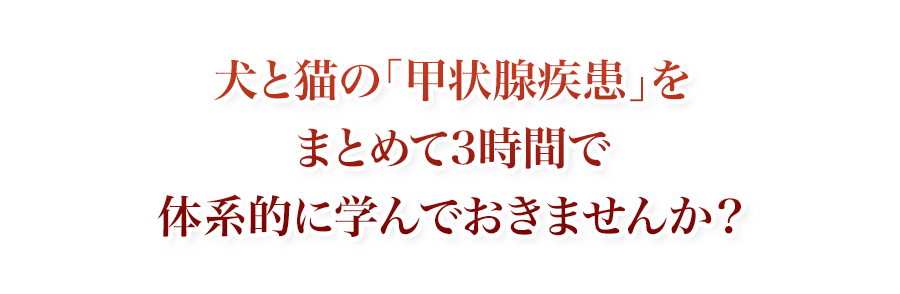
From:〇〇
日付:2025年9月8日12:00
※ホームドクターの「2人に1人が誤診する」事実
獣医療は、この数十年で目覚ましい進歩を遂げました。かつては難病とされた疾患でも、正しい診断さえできれば、何らかの治療を提供できる時代になったのです。
「診断こそが動物の生命を左右する」。
そう言っても、決して大げさではありません。
しかし、2024年。ある衝撃的な論文が発表されました。
一次診療で「甲状腺機能低下症」と診断され、レボチロキシン(チラージン)を投与された102頭の犬を調査した結果、「約半数が誤診、または確かな診断とは言えない」と結論付けられたのです(Travail V et
al., J Vet Intern Med. 2024)。
検査結果を鵜呑みにしたまま診断を進めた結果、本当は必要のない薬を犬に投与してしまい、副作用を引き起こしていた。
そんな事実を、この論文は浮き彫りにしたのです。では先生は、「自分は大丈夫。誤診はしない」と自信を持って言い切れますか?
もし、こんな診療をしているのなら、注意しなくてはなりません。

講師紹介
森 昭博先生
もり あきひろ
- 日本獣医生命科学大学 獣医学部
- 獣医保健看護学科 准教授
- 日本獣医生命科学大学付属動物医療センター 内分泌科
Profile
日本獣医畜産大学(現:日本獣医生命科学大学)獣医学部獣医学科卒業後、同大学大学院で博士号(獣医学)を取得。2012年にイリノイ大学に留学し、最先端の動物栄養学の研究に従事。現在は、日本獣医生命科学大学付属動物医療センターにて、内分泌科を担当している。
- 【表彰歴】
- 2008年10月
- Eitan Bogin Prize
(2008年国際動物臨床病理学会ベストポスター賞) - 2017年4月
- 日本獣医生命科学大学梅野信吉賞
- 2023年4月
- 日本獣医生命科学大学紫雲賞(ベストティーチャー賞)
- 【セミナー・講演歴】
- 獣医内科学アカデミー
- 動物臨床医学会
- 日本臨床獣医学フォーラムなど
健康診断で来院した、10歳のトイプードルのお話です。
飼い主さんに普段の様子を尋ねると、食事や排泄には問題なし。
ただ、「最近、少し元気がない気がするんです。年齢のせいでしょうか…」と心配されていました。
ドクターは丁寧に身体検査をおこない、さらに尿検査、画像検査、血液生化学検査も実施。その結果、T4(甲状腺ホルモン)の数値が正常より低いことがわかりました。「これは甲状腺機能低下症だろう」。
そう考えたドクターは、甲状腺機能低下症と診断し、チラージンによる治療を開始しました。
しかし、数週間が経過しても犬の元気は戻りません。それどころか、最近は落ち着きがなくなり、水を飲む量も増えてきたと飼い主さんは訴えました。
原因がわからず、ドクターは二次診療施設への紹介を決断。そこでの精査で明らかになったのは、この犬には下垂体腫瘍があり、それによりT4が低下していたという事実でした。
つまり、甲状腺機能低下症ではなく、下垂体腫瘍による二次的なT4低下だったのです。チラージンの投与は本来不要で、むしろ副作用として多飲多尿が悪化していたのでした。
「検査値だけを信じてはいけなかった…」。心の中で、ドクターは何度もそう呟いたといいます。
今お話したのは、一次診療の現場でよくある間違いをもとにしたフィクションです。
ただ、 「誤診率50%」の事実が示す通り、このようなミスは決して珍しくありません。
診断ミスは、本来必要のない薬を投与し、副作用で症状を悪化させるだけでなく、飼い主さんの信頼を大きく損なう原因になります。
「先生に診てもらったのに、うちの子は余計に具合が悪くなった…」。そんな声が広がれば、病院の評判にも直結します。
甲状腺疾患は、正しく診療できれば症状が劇的に改善し、犬猫が元気を取り戻すだけでなく、飼い主さんから「先生のおかげです!」と感謝されるケースが多い疾患です。
つまり、甲状腺疾患を専門的に学ぶことは、犬猫と飼い主さんを救うだけでなく、先生の診療に対する信頼をより強固にするためにも、重要な取り組みと言えます。
本教材は、国内屈指の内分泌疾患のスペシャリストである森先生から、「犬と猫の甲状腺疾患診療」を体系的にわかりやすく学べます。
- AAHAガイドラインの注目ポイント
- 甲状腺機能低下症を誤診しやすい理由
- 甲状腺ホルモンの生理的作用
- 甲状腺ホルモンが生成されるメカニズム
- なぜ、T4・FT4・TSHを測定するのか?
- TSHは、万能なのか?
- Euthyroid sick syndromeとは、何か?
- 高カルシウム血症を主訴に来院した犬の症例
- 典型的な甲状腺機能低下症の犬の症例
- クッシングのときの甲状腺機能低下症
- ナックリングが生じている犬の症例
- 猫の甲状腺機能亢進症の病態生理
- 一般身体検査のポイントと注意点
- どんどん痩せていく猫の症例
- 猫の甲状腺機能亢進症の臨床症状とは?
- 甲状腺ホルモンの測定評価法
- 猫の甲状腺機能亢進症の治療
- 体重低下が続く猫の症例
- 甲状腺機能亢進症の治療経過
- 術後管理のポイントと注意点
- 甲状腺機能亢進症とCKDの関係とは?
- 体重低下のない甲状腺機能亢進症の猫の症例
- 食欲はあるのに痩せていく猫の症例
- 手術希望で来院した猫の症例
- 息が荒い・削痩で来院した猫の症例
9月17日(水)12:00にお申し込み専用ページをご案内しますので、
今しばらくお待ちください。